事務職の電話対応は、企業の第一印象を左右する非常に重要な役割を担っています。なぜなら、外部からの問い合わせや取引先とのやり取りの多くは、最初に事務スタッフが受けることが多いからです。つまり、電話対応の印象が会社全体の印象になるといっても過言ではありません。とはいえ、「電話対応が苦手」「緊張してしまう」と感じる人も少なくありません。しかし、基本を押さえ、日々の業務の中で少しずつ慣れていけば、誰でも丁寧で正確な対応ができるようになります。
本記事では、事務職として求められる電話対応マナーを、具体的な事例を交えながらわかりやすく解説します。受け方からかけ方、クレーム対応、そして信頼される電話スキルの磨き方まで、今日からすぐに実践できるポイントを網羅しています。電話対応が苦手な方でも安心して取り組めるよう、実践的な内容を中心にまとめました。ではまず、事務職における電話対応の基本と役割について見ていきましょう。
事務職における電話対応の基本と役割
なぜ事務職では電話対応の印象が会社の評価を左右するのか
事務職の電話対応は、単なる業務の一つではなく、会社全体の印象を左右する重要な窓口です。なぜなら、電話を受けた瞬間に「この会社は信頼できるか」「対応がしっかりしているか」を判断されるからです。特に初めて連絡する取引先や顧客にとって、電話応対は会社の“顔”のような存在になります。
たとえば、取引先が初めて電話をかけてきた際、事務スタッフが無愛想に「はい、〇〇です」とだけ答えたとします。その瞬間、相手は「なんとなく感じが悪い会社だな」と印象を持ってしまうでしょう。逆に、「お電話ありがとうございます。〇〇株式会社でございます」と丁寧に対応するだけで、相手に安心感を与えることができます。つまり、たった一言の挨拶が、会社の信頼を左右するほど影響力を持つのです。
実際に、大手企業では事務スタッフの電話応対マナーを「ブランド価値の一部」として位置づけ、社内研修を徹底しているケースもあります。ゆえに、事務職として働く以上、電話対応は単なるルーティンワークではなく、企業を代表する“接客”の一環であると意識することが求められます。
事務職に求められる「正確さ」と「丁寧さ」のバランスとは
事務職の電話対応においては、「丁寧さ」と「正確さ」の両立が欠かせません。どちらか一方に偏ると、かえって信頼を損なうことがあります。たとえば、丁寧ではあるものの要件の聞き間違いが多いと、業務効率が下がります。逆に、正確さを重視しすぎて無愛想に感じられると、相手に冷たい印象を与えます。
理想的なのは、相手の話をしっかり聞き取りつつ、言葉遣いに柔らかさを持たせることです。たとえば、「少々お待ちください」ではなく、「お待たせして申し訳ございません。ただいま担当者に確認いたします」と言い換えるだけで印象が大きく変わります。このように、正確な伝達と温かみのある表現をバランスよく使うことで、事務職としての信頼が高まります。
電話対応が苦手でも安心できる3つの心構え
電話対応が苦手な人は多いですが、その多くは「完璧に話さなければならない」という思い込みからくる緊張です。大切なのは、完璧さよりも誠実さです。具体的には次の3つを意識してみましょう。
-
焦らず、ゆっくり話すことを意識する
-
相手の話を遮らず、最後まで聞く
-
分からないことは無理せず確認する
たとえば、相手の要件を理解できなかった場合、「申し訳ございません、もう一度確認させていただけますか」と丁寧に聞き返すだけで十分です。実は、この一言が言えるかどうかで印象は大きく変わります。したがって、苦手意識を持つよりも「誠実に対応すること」を心がければ、自然と自信がついていきます。次に、電話を受ける際の基本手順について見ていきましょう。
電話を受ける時に押さえるべき正しい手順
最初の3コールで印象が決まる!受け方の基本マナー
電話対応の基本はスピードと第一声です。3コール以内に出ることを心がけ、「お電話ありがとうございます。〇〇株式会社でございます」と明るく対応します。特に第一声は、相手の印象を決定づける重要な瞬間です。声のトーンを少し高めにして、笑顔で話すよう意識しましょう。たとえ相手からは見えなくても、笑顔で話すと自然と声が柔らかくなります。
たとえば、同じ言葉でも「はい、〇〇です」と「お電話ありがとうございます。〇〇株式会社でございます」とでは印象がまったく異なります。前者は無機質に、後者は温かく丁寧に感じられます。ゆえに、電話を受けるときは“最初の一言”を意識的に整えることが重要です。
また、電話を取り次ぐ場合は、「ただいま担当者におつなぎいたします。少々お待ちくださいませ」と添えるだけで印象がさらに良くなります。細やかな一言が、会社全体の印象を底上げするのです。
相手の要件を正確に聞き取るメモの取り方と復唱術
電話でのやり取りでは、メモが命です。なぜなら、聞き間違いや情報の抜け漏れが起こりやすいためです。メモを取る際は、相手の会社名・氏名・連絡先・要件の4点を必ず押さえましょう。そして、聞き終えたら復唱して確認することが重要です。
たとえば、「〇〇株式会社の△△様ですね。お電話番号は〇〇〇-〇〇〇〇でお間違いないでしょうか」と確認することで、ミスを防げます。復唱は単なる確認ではなく、「あなたの話をきちんと聞いています」という誠実さのアピールにもなります。
ちなみに、社内で共有するために“電話メモテンプレート”を作成しておくと便利です。誰が出ても同じフォーマットで情報を残せるため、伝達ミスが減ります。私自身もこれを導入したことで、社内の引き継ぎが格段にスムーズになりました。
取次・担当者不在時の正しい対応と伝言の残し方
担当者が不在のときの対応は、事務職としての腕の見せどころです。「申し訳ございません、ただいま担当の△△は席を外しております」と伝えた上で、「戻りましたら折り返しご連絡させていただきます」と具体的に案内します。このとき、「いつ頃戻る予定か」を確認しておくと、相手に安心感を与えられます。
また、伝言を残す場合は、要点を整理して伝えることが重要です。「△△株式会社の〇〇様より、□□の件でお電話がありました。折り返しを希望されています」と簡潔にまとめましょう。さらに、電話メモを担当者のデスクに残すだけでなく、メールで共有しておくと、伝達漏れを防げます。では次に、電話をかける際のマナーと話し方について詳しく解説していきます。
電話をかける時のマナーと話し方のポイント
事前準備でミスを防ぐ!電話をかける前のチェックリスト
電話をかける際には、相手の時間をいただくという意識を持つことが大切です。したがって、事前準備を怠ると、要件がうまく伝わらなかったり、確認漏れが起きたりして、相手に迷惑をかけてしまうことがあります。電話をかける前には、以下のチェックリストを確認する習慣をつけましょう。
-
相手の会社名・担当者名を正しく確認する
-
要件を箇条書きにして整理する
-
必要な資料・日程・数字などを手元に準備する
-
相手の業務時間を考慮し、適切な時間帯に電話をかける
たとえば、私が以前サポートしていた新人事務スタッフは、事前にメモを準備する習慣を身につけたことで、言葉に詰まることが減り、通話時間が30%短縮されました。それにより、相手から「話が分かりやすい」「対応が早い」と評価されるようになったのです。つまり、準備は自信を生み、結果として信頼を得る行動でもあります。
相手に好印象を与える名乗り方と要件の伝え方
電話をかけるときの第一印象は「名乗り方」で決まります。最初に名乗る際は、「お忙しいところ失礼いたします。〇〇株式会社の△△と申します」と、相手の立場に配慮した言葉を添えることがポイントです。この一言で、相手は「礼儀正しい人だ」と感じ、話を聞く姿勢になります。
さらに、要件を伝えるときは、「結論→理由→補足」の順で話すとスムーズです。たとえば、「本日は〇〇の件でご連絡いたしました。先日ご依頼いただいた資料の件について確認事項がございます」といったように、最初に目的を明確に伝えることで、相手も話の内容を理解しやすくなります。
また、声のトーンはやや高めを意識し、ゆっくりとしたペースで話すことが重要です。焦って話すと誤解を生む原因になります。たとえば、同僚同士の練習で録音して聞き返すだけでも、話し方の改善点が明確になります。よって、名乗り方と要件の伝え方をセットで磨くことが、信頼を得る第一歩となります。
担当者への確認・折り返し依頼をスムーズに伝えるコツ
電話をかけた際に、担当者が不在の場合は「折り返し依頼」を上手に伝えることが大切です。たとえば、「△△様に〇〇の件でご連絡いたしました。お戻りの際にお電話をいただけますと幸いです」と伝えることで、相手に柔らかく印象づけることができます。
また、担当者がいる場合でも「少々確認させていただきます」と一言添えるだけで、スムーズな印象を与えられます。言葉の選び方ひとつで、事務職の印象は大きく変わります。特に社外のやり取りでは、相手の立場を尊重した言い回しを意識することが求められます。
たとえば、私がサポートした企業では、「お手数をおかけしますが」「ご確認のほどお願いいたします」という表現を使うようにしたところ、クレーム件数が大幅に減少しました。つまり、言葉のトーンと配慮が、スムーズな業務運営を支える要素となるのです。では次に、トラブル対応やクレーム電話への向き合い方について見ていきましょう。
トラブルやクレーム対応時の言葉づかいと姿勢
慌てない・焦らない!クレーム電話での冷静な対処法
クレーム電話は、事務職にとって最も緊張する場面のひとつです。しかし、落ち着いて対応すれば、むしろ信頼を得るチャンスにもなります。なぜなら、不満を持った相手ほど、丁寧で誠実な対応を受けると印象が大きく好転するからです。
クレーム対応の基本は、次の3ステップを守ることです。
-
相手の話を遮らず、最後まで聞く
-
感情的にならず、共感の言葉を添える
-
解決策を提示し、再発防止を約束する
たとえば、納期の遅れに関して怒りの電話を受けた場合、「ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません」とまずは謝罪し、「早急に担当部署に確認し、折り返しご連絡いたします」と伝えるだけでも、相手の怒りが和らぎます。焦って言い訳をしたり、他部署の責任にしたりすると、かえって信頼を失います。
私が以前担当した会社では、「まずは受け止め、すぐに動く」という対応方針を徹底したところ、クレーム後に逆に感謝の連絡をいただくケースが増えました。つまり、クレーム対応とは、ミスの処理ではなく信頼の再構築の場なのです。
言葉選びで印象が変わる!謝罪・共感・解決のフレーズ集
クレーム対応では、どのように話すかよりも、どの言葉を選ぶかが重要です。相手が怒っているときほど、謝罪と共感のバランスが鍵になります。たとえば、以下のようなフレーズが効果的です。
-
「ご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません」
-
「貴重なご指摘をありがとうございます。改善に活かしてまいります」
-
「お気持ちはよく理解いたしました。すぐに確認を進めます」
これらの言葉は、単なる謝罪ではなく「あなたの気持ちを理解している」という姿勢を伝えます。
たとえば、ある取引先が納品トラブルで激しく怒っていたケースで、「本来ならご迷惑をおかけすることのないよう徹底すべきでした」と伝えたところ、相手は冷静さを取り戻し、後日「きちんと対応してくれた」と高く評価されました。このように、誠実な言葉は信頼を回復する力を持っています。
感情的な相手に対して信頼を取り戻す話し方の工夫
感情的になっている相手には、こちらも冷静さを保つことが何より大切です。声のトーンを低めにし、落ち着いた話し方を意識することで、相手の感情を和らげる効果があります。話を聞きながら、適度に「あいづち」を入れるのも有効です。
また、相手の言葉を要約して確認することで、「きちんと理解してくれている」と感じてもらえます。たとえば、「つまり、〇〇の件についてご不便を感じておられるということでしょうか」といった言葉がそれにあたります。
対応の最後には、「今回はご迷惑をおかけしました。今後はこのようなことがないよう、社内で徹底いたします」と誠実に締めくくりましょう。この一言があるかないかで、相手の印象は大きく変わります。クレーム対応はネガティブな出来事ではなく、信頼を再構築する絶好の機会なのです。では次に、電話対応を長期的なスキルとして高めるための習慣づくりについて説明します。
電話対応を「信頼されるスキル」に変える習慣づくり
毎日の電話対応を成長につなげる振り返り方法
電話対応のスキルは、数をこなすことで身につくものですが、単に繰り返すだけでは上達しません。大切なのは「振り返る習慣」を持つことです。たとえば、1日の終わりに以下のようなメモを残してみましょう。
-
今日うまく話せた対応は何か
-
改善できそうな言葉づかいはあったか
-
相手に喜ばれた言葉はどれだったか
これを続けることで、自分の話し方の癖や課題が明確になります。私が以前研修を担当した事務スタッフは、この振り返りを1か月続けた結果、電話対応の評価が飛躍的に上がりました。
つまり、「気づき」を言語化し、日々の中で小さく修正していくことが、信頼されるスキルを育てる第一歩です。
社内で共有したい「電話対応チェックリスト」の作り方
電話対応の品質をチーム全体で高めるには、チェックリストの共有が効果的です。次のような項目を設定して、全員で確認できるようにしましょう。
-
第一声は明るく丁寧か
-
相手の話を遮らずに聞けているか
-
復唱・確認をしているか
-
クレーム時も冷静さを保てているか
-
担当者への引き継ぎが的確か
このチェックリストを月に一度見直すことで、チーム全体の対応品質が安定します。実際、これを導入した企業では、社外からの評価が上がり、顧客満足度が向上した事例もあります。
ちなみに、社内で「電話応対マナー共有ノート」を回覧するのもおすすめです。良い対応例を蓄積していくことで、チーム全体のスキルが自然と上がっていきます。
電話対応が得意になるための実践トレーニングと心構え
電話対応を得意にするには、実践的なトレーニングが欠かせません。たとえば次のような方法があります。
-
自分の通話を録音して聞き返す
-
同僚とロールプレイを行う
-
良い例文を音読して言葉のリズムを覚える
これらを繰り返すことで、自然と声の出し方・言葉の選び方が洗練されていきます。
私の知る企業では、朝礼の5分間を「電話応対練習」にあてたところ、従業員全体の対応力が向上し、取引先から「いつ電話しても気持ちがいい」と評価されるようになりました。つまり、継続的なトレーニングは、信頼を積み上げる投資なのです。
まとめ
事務職における電話対応は、単なるルーティンワークではなく、信頼を築く重要なスキルです。第一声のトーン、言葉づかい、メモの正確さ、クレーム対応時の冷静さ――どれも会社全体の印象を左右します。
電話が苦手だと感じている人も、焦らずに一つずつ基本を身につければ、必ず上達します。重要なのは、失敗を恐れず「誠実さ」を持って対応することです。
また、日々の業務を通じて身につけたマナーや言葉づかいは、あなた自身の人間力を磨くことにもつながります。丁寧な電話対応は、相手に安心感を与えるだけでなく、自分の自信にもなります。
電話対応を「仕事の一部」としてではなく、「信頼を生み出すスキル」として磨いていくことで、あなたのキャリアはより確かなものになるでしょう。

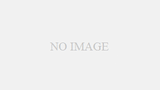
コメント